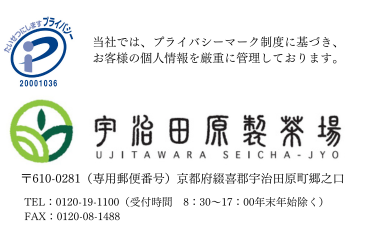こんにちはゲスト 様
営業日カレンダー
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
300年前の医学書『養生訓』に学ぶ、健康長寿のススメ5選!
2025.11.01
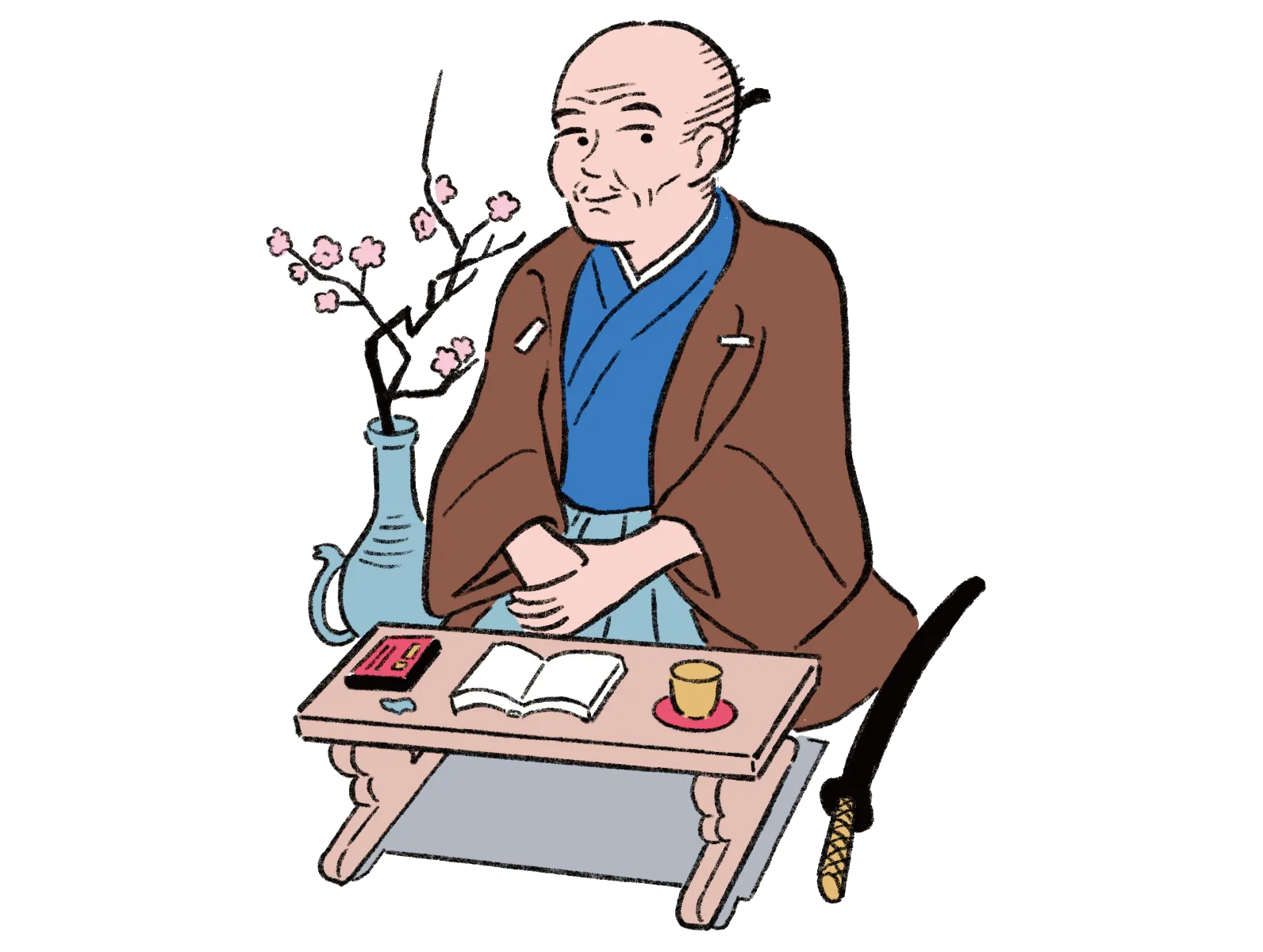
人生100年時代が叫ばれる昨今。健康に長生きしたいと多くの方が望む現代で、300年前の医学書が今、注目を集めています。その名も『養生訓』は、江戸時代の儒学者・貝原益軒(かいばらえきけん)が健康長寿の心得を記したもの。現代にも通じるその考え方を5つご紹介します。
目次
1.『養生訓』ってどんな書物?
貝原益軒によって書かれた健康で長生きするための心得が綴られた全8巻の書物です。平均寿命が40歳前後の江戸時代において、85歳まで生きた益軒が、生涯を通じて追求してきた養生体験と、そこから得た教訓が平易な言葉で書かれています。正徳3年(1713)に出版されて以来、日本でもっとも広く、長く読み継がれてきた医学書の古典です。
2.著者の貝原益軒ってどんな人?
江戸時代の儒学者、博物学者、庶民教育家です。寛永7年、福岡藩で生まれ、幼い頃は父の転職で各地を転居していました。2代目福岡藩主に仕えていましたが、後に浪人となり、医者として身を立てようと医学修業に励みました。壮年期には藩に再就職し、京都に数年間、留学し、朱子学を学び、晩年には『養生訓』『大和俗訓』など多くの教訓書を書いています。
3.『養生訓』の中から、健康のススメを5つご紹介!
健康のススメその1:養生は習慣。慣れれば苦労でなくなる。
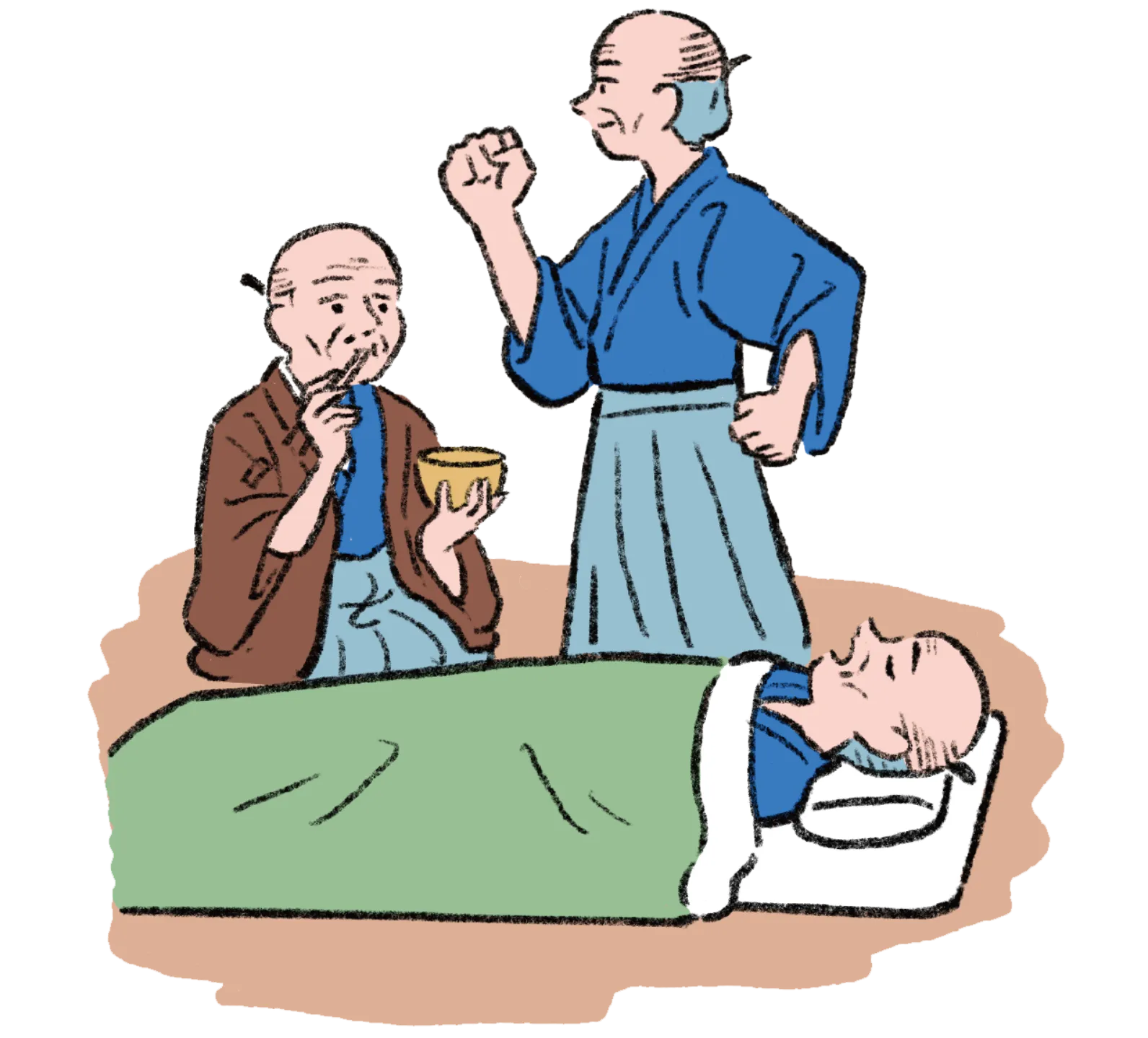
「凡よき事あしき事、皆ならひよりおこる。養生のつつしみ、つとめも亦しかり。」(巻第二総論下)
よいことも悪いことも、習慣から起こります。養生もそうです。欲求や感情を抑えるのは大変そうに思えますが、続けて習慣にしてしまえばつらくありません。
逆に、からだによくないことを習慣にしてしまうと、いざ養生しようと思っても苦しくて耐えられなくなってしまいます。寝る、食べる、動く。養生のために、日々の習慣にしてしまうことが大切です。
健康のススメその2:冬こそ、頭寒足熱。
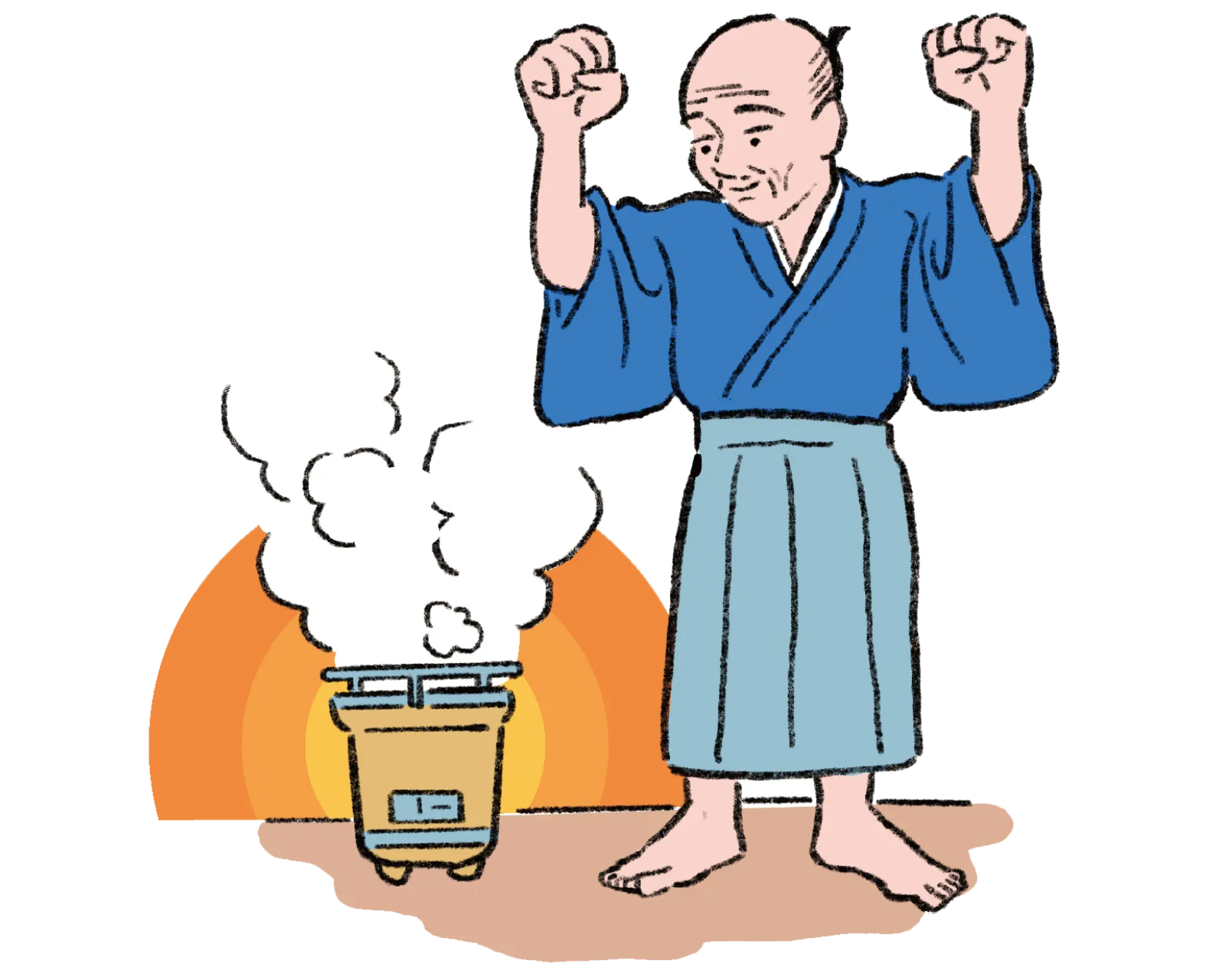
「冬は、天地の陽気とぢかくれ、人の血気、をさまる時也。心気を閑かにし、おさめて保つべし。」(巻第六慎病)
冬は陽気が閉じ、活力がなくなるときです。からだから活力を逃がさないようにしましょう。温めすぎると上半身だけに熱がこもり、下半身が冷えてしまうので、あまり重ね着や厚着をせず、暖房もほどほどにしましょう。
熱すぎるお風呂に入るのもよくありません。運動や熱いものを食べて汗をかいたら、汗で冷えることのないように気をつけましょう。
健康のススメその3:養生は健康な胃腸から。
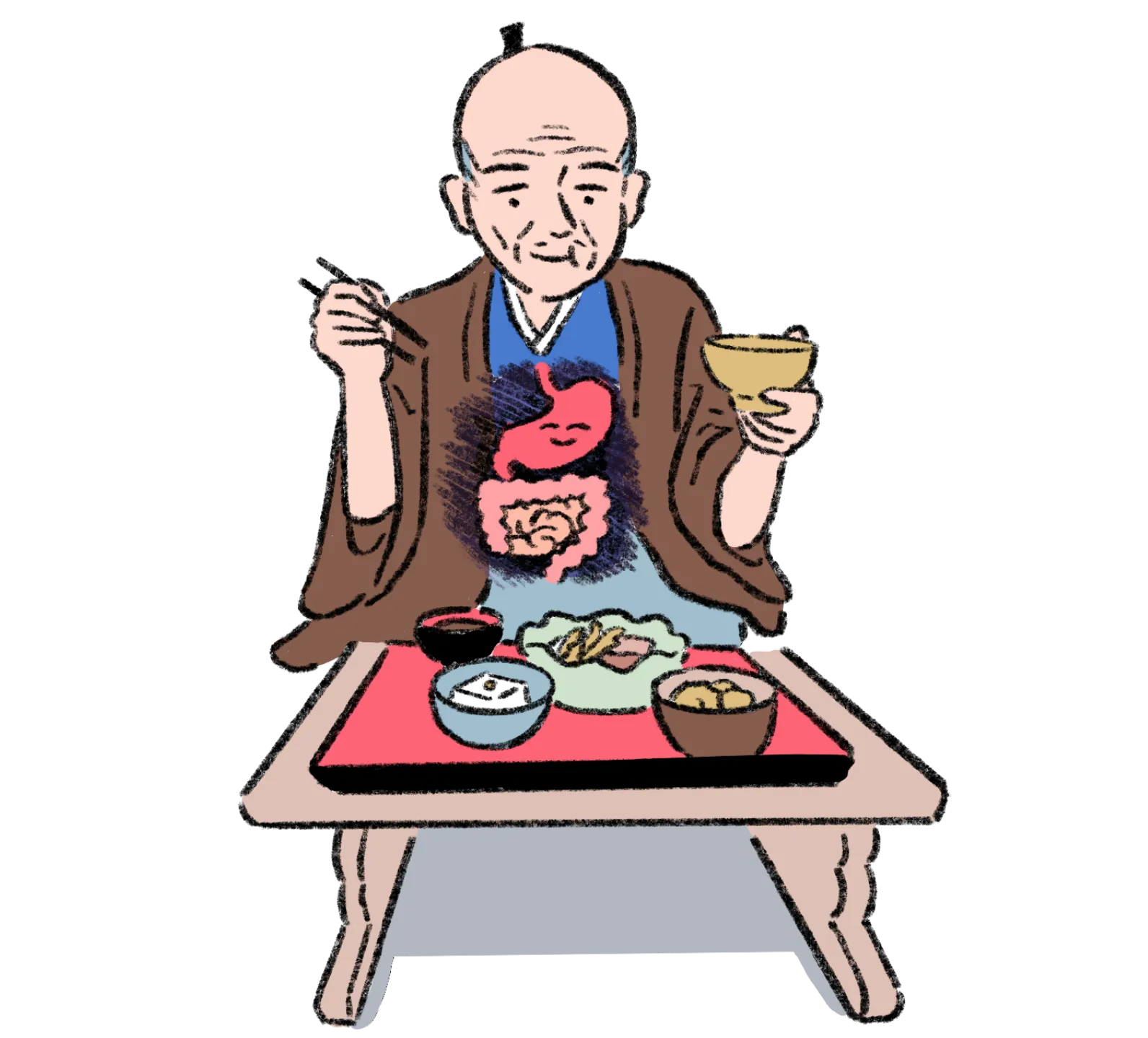
「脾胃を調るは、人身第一の保養也。」(巻第三飲食)
人は食べたものを胃腸で消化し、からだに栄養を送ることで命をつないでいます。だから、養生を志す人は、まずは胃腸を調えるべきです。
けれども、食への欲求は非常に強いものです。気の赴くままに飲み食いしたら、胃腸を壊してしまいます。好物であっても腹八分目。満腹を避けることが大切です。
食事はご飯を中心にして、甘い、辛い、塩辛い、苦い、酸っぱいの5つの味をバランスよく食べるとよいでしょう。
健康のススメその4:自分でできることは、自分で動く。
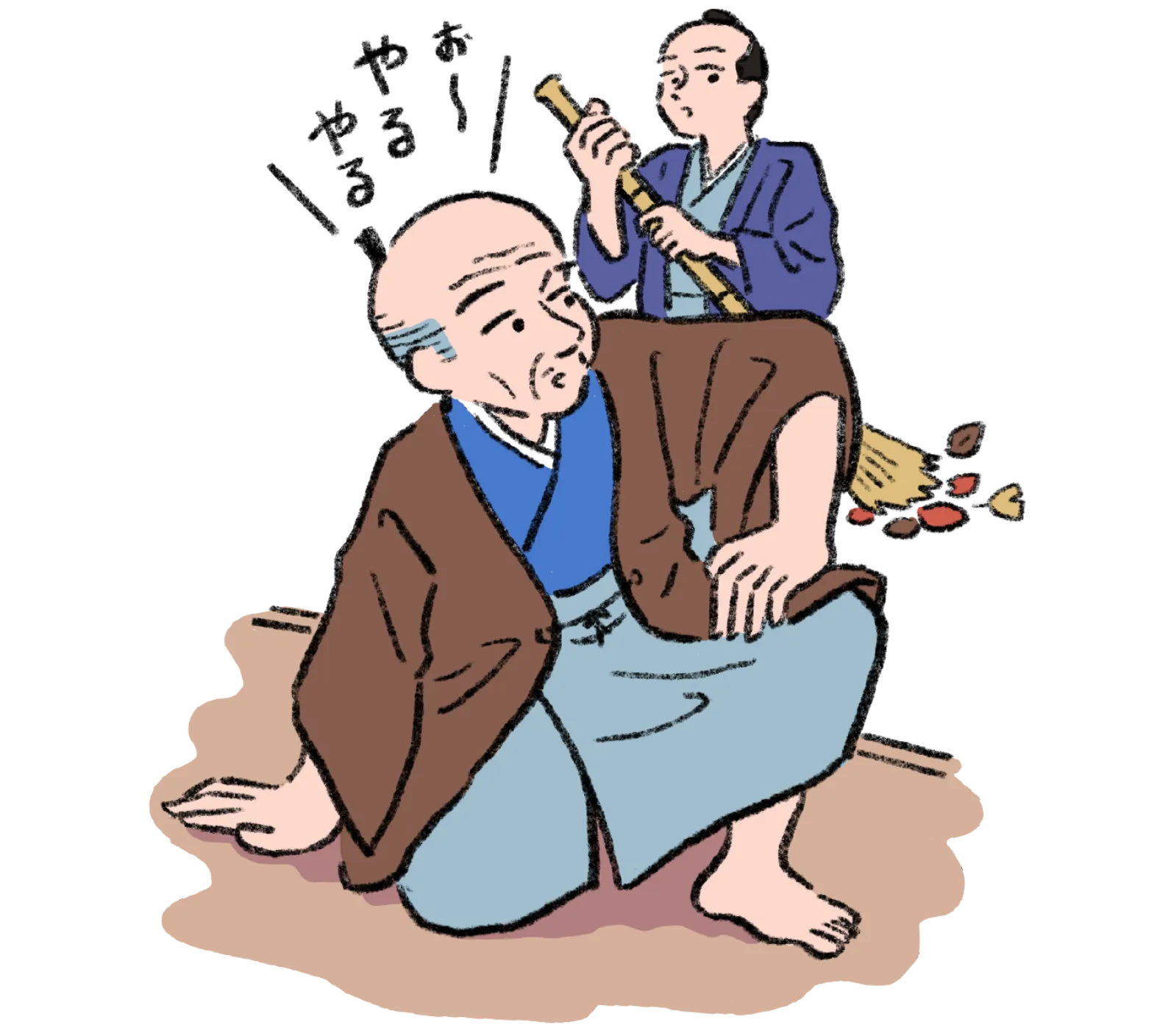
「家に居て、時々わが体力の辛苦せざる程の労働をなすべし。」(巻第二総論下)
家にいるときは、自分の体力がつらくならない程度に運動しましょう。立ったり座ったりを面倒がらずに、家のことは自分でするといいです。そうしていつもからだを動かしていると、活力が出てきて食欲も湧きます。
動きっぱなしもつかれますが、一日中座っていたり、寝ていたりするのも問題です。動も静も長すぎるのはよくありません。運動などで汗をかいたら、風に当たって冷えることのないようにしましょう。
健康のススメその5:老後は一日千金。いつでも楽しもう。
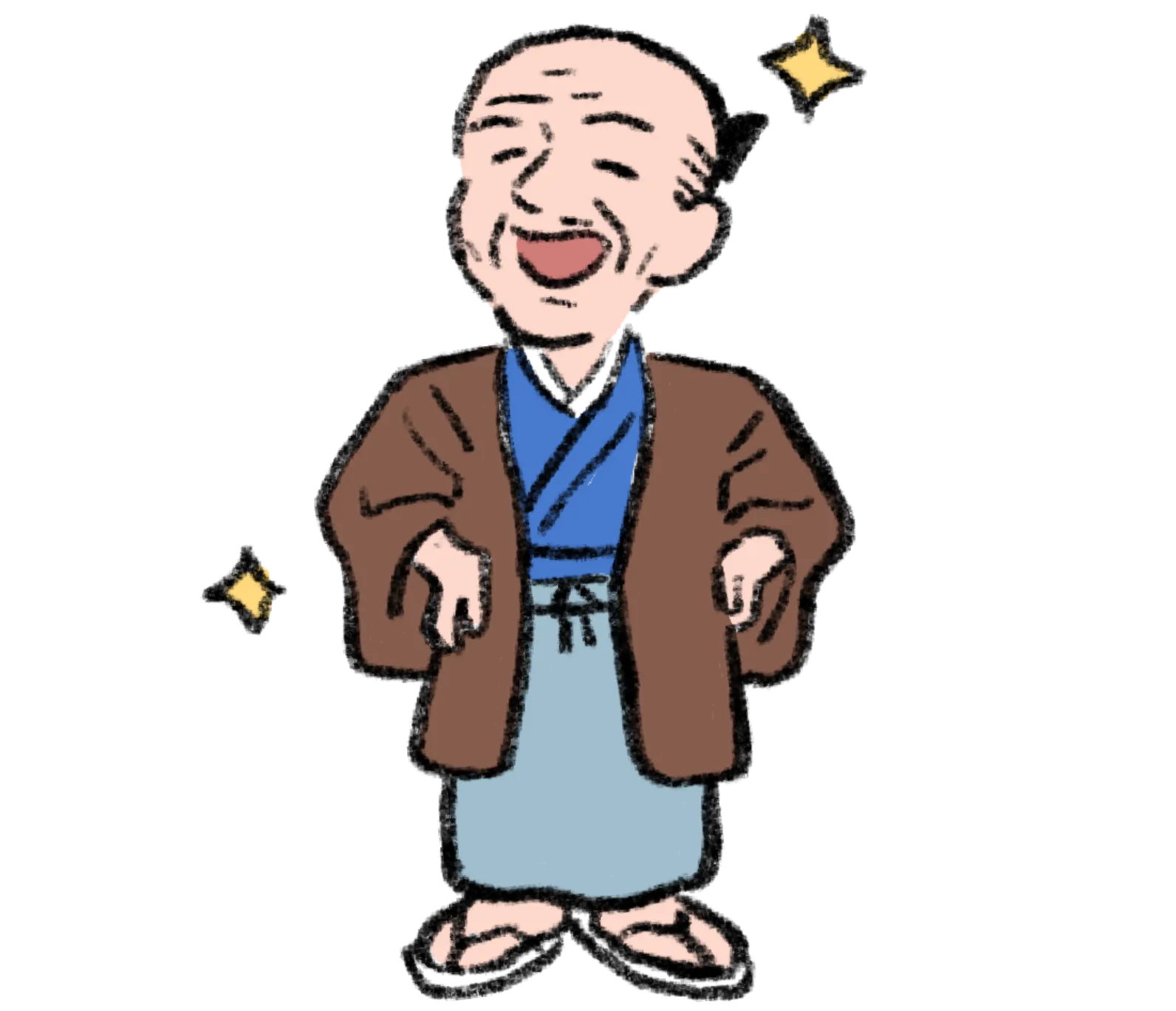
「老後一日も楽まずして、空しく過すはおしむべし。」(巻第八養老)
老後は若いときの10倍の速さで時が過ぎてしまいます。1日を10日分生きるつもりで、人生を楽しみたいものです。
世間の空気が気に食わなくても、そういう人たちだからとやり過ごし、誰かが間違いや失敗をしても、あたたかく許してしまいましょう。
生活に余裕がないとか、他人に理不尽なことをされても気に病まないようにしましょう。世の中はこういうものだと受け入れ、心穏やかに過ごしたいものです。
老後は毎日が一日千金。たとえ1日でも後ろ向きな気分で過ごすなんてもったいないです。
暖かい日には庭に出て草木を愛したり、読書をしたり、俳句や短歌などの趣味を楽しんだりして、心を充実させましょう。人生を楽しむことも、立派な養生の一つです。

4.まとめ
江戸時代の儒学者・貝原益軒によって300年前に記された『養生訓』。その中からご紹介した5つの健康のススメは、いかがだったでしょうか。
『養生訓』には、現代にも通じる健康長寿の知恵がたっぷりと詰まっています。変化の激しい時代だからこそ、シンプルで本質的な「養生」の考え方を、日々の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。
人生100年時代を健やかに生き抜くヒントが、そこにはきっとあるはずです。