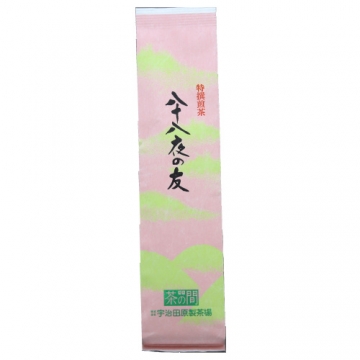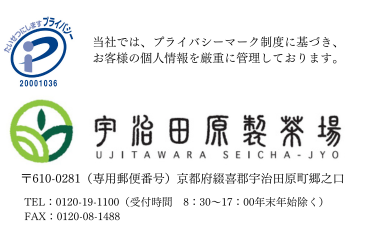こんにちはゲスト 様
営業日カレンダー
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
千利休も仰天!これまでの常識が変わる、お茶の歴史にまつわる新発見!
2025.05.01
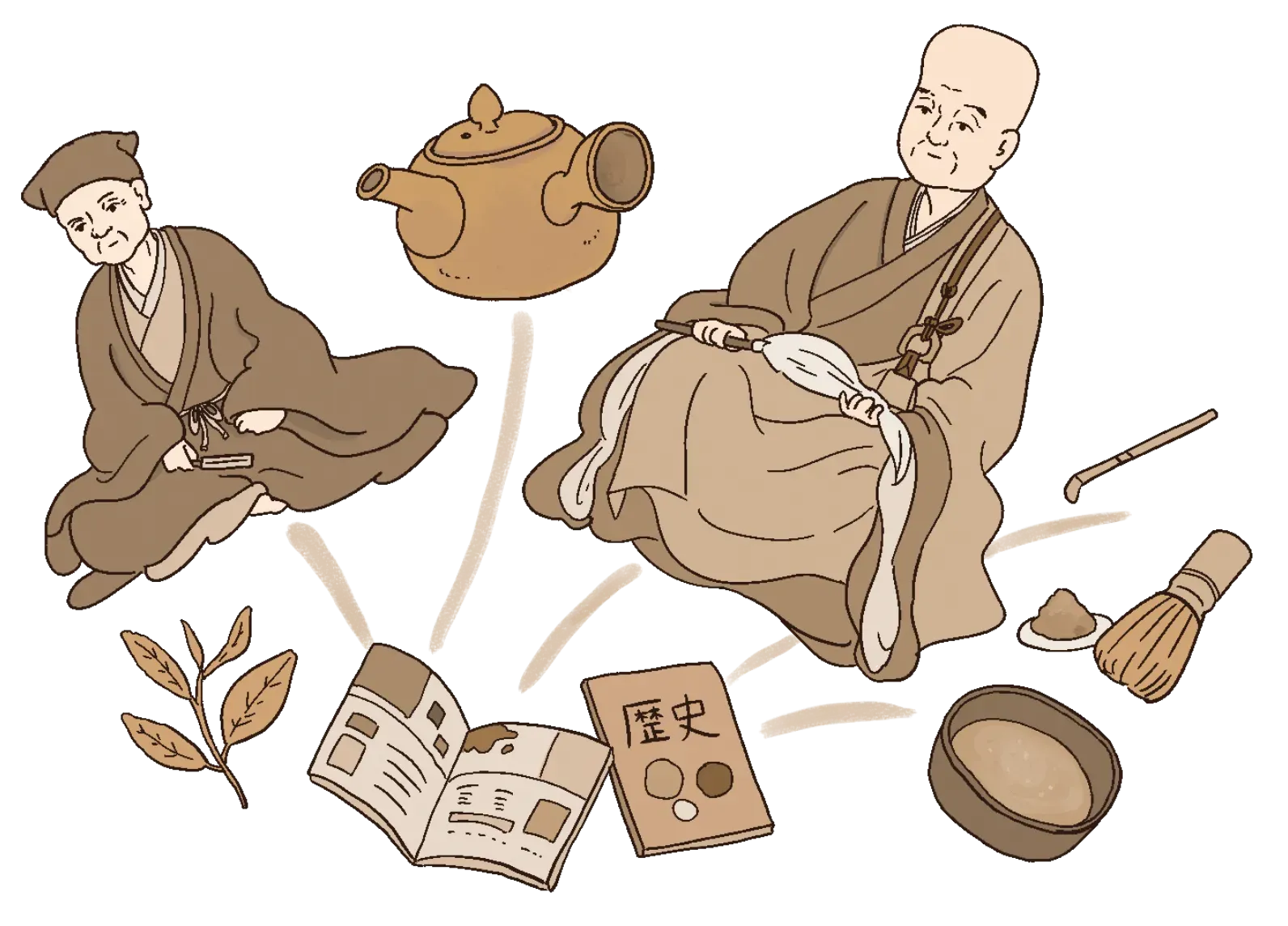
私たちが知っているお茶の歴史の定説は、最新の研究によってすでに更新されていたり、見直されていたりすることがあります。日本のお茶の歴史を研究し続けて30年以上の、中村修也先生をナビゲーターに迎え、最前線のお茶の歴史研究についてご紹介します。

教えてくれた人
文教大学教授 中村修也 先生
1959年、和歌山県生まれ。筑波大学卒業。同大学院博士課程単位取得終了。文学博士。京都市歴史資料館勤務を経て文教大学教育学部教授。専門は日本文化史。著書に『平安京の暮らしと行政』(山川出版社)、『戦国茶の湯倶楽部―利休からたどる茶の湯の人々』(大修館書店)、『千利休 切腹と晩年の真実』(朝日新書)、編著書に『講座 日本茶の湯全史 第一巻 中世』(思文閣出版)など。
1.なんと!お茶は平安時代にも飲まれていた!
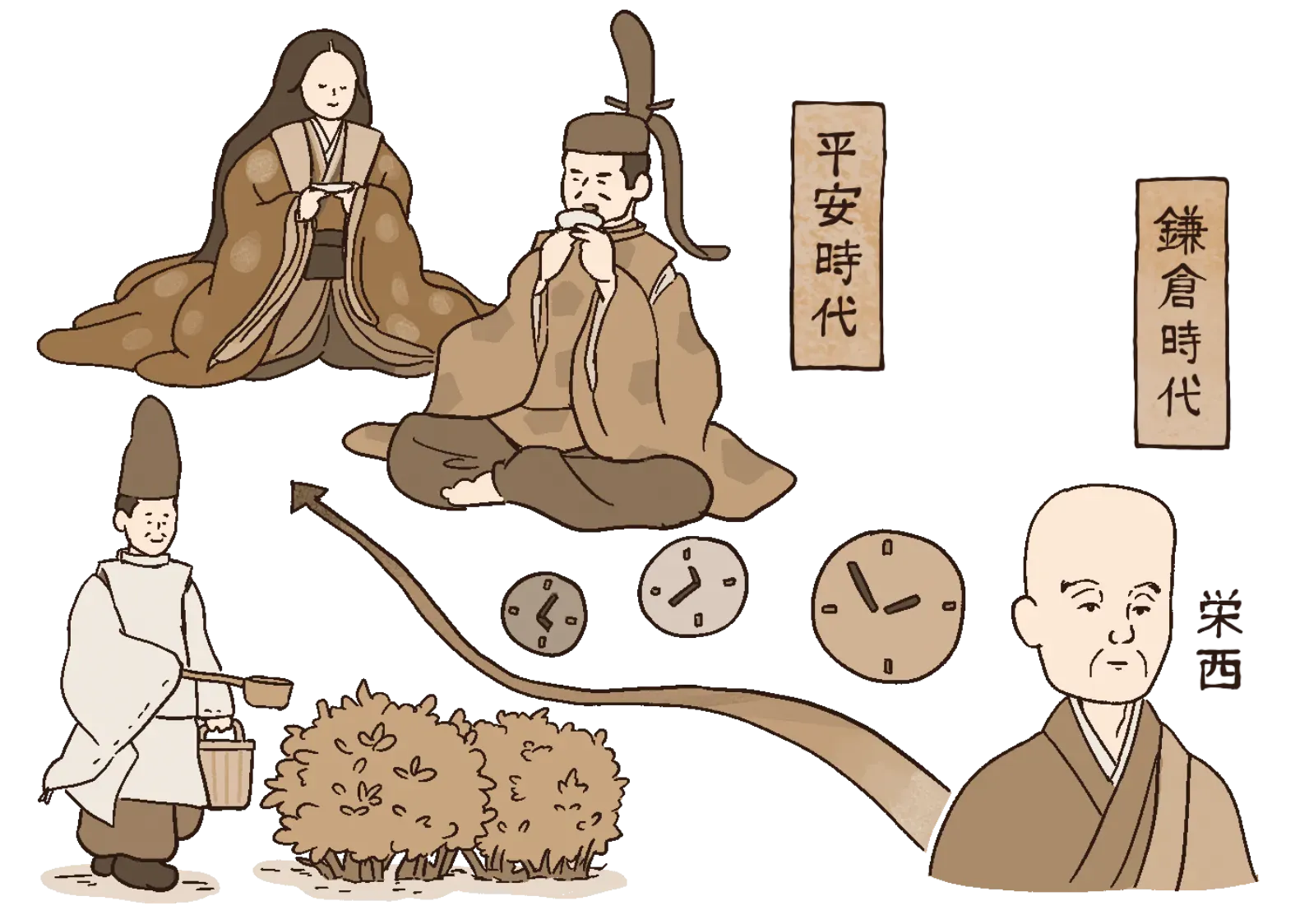
公家の日記にもお茶の記録があった!
日本でお茶に関する最も古い史料は、弘仁6年(815)、嵯峨天皇が近江国の梵釈寺(ぼんしゃくじ)に御幸した際、留学僧の永忠(えいちゅう)が自らの手で天皇に献茶したという記録です。翌年、嵯峨天皇が近畿諸国に茶を植樹させたという記録もあります。ただ、その後日本ではお茶は定着せず、鎌倉時代に禅僧の栄西が中国からお茶を導入してようやく普及したというのが定説です。
しかし、中村先生によると、貴族の日記や儀礼書などにはお茶に関する記録があり、平安貴族はお茶を飲んでいたというのです。
平安時代の宮中では国家安泰のため「季御読経(きのみどきょう)」という大般若経を輪読する法会を定期的に行ない、その際、引茶(ひきちゃ)という僧侶へのお茶のふるまいがあったそうです。引茶には、甘味料としての甘葛煎(あまづらせん)や生姜も入れていました。このお茶はもちろん抹茶ではなく、茶葉を熱湯に投じて淹れる煮茶(にちゃ)だろうとのこと。2024年度NHK大河ドラマ「光る君へ」で描かれた中宮定子も中宮御読経を行なったというお茶の記録があります。
公卿(くぎょう)だった藤原実資(さねすけ)の日記「小右記(しょうゆうき)」には、藤原道長が体調不良の際、御簾(みす)に何度も出入りしてお茶を飲んでいた様子も描かれています。また菅原道真も大宰府でお茶を漢詩に詠んでいて、一部の貴族の手元にはお茶があったことが伺えます。
記録には宮城内にある「造茶所」や「茶園」などの語もあり、お茶は宮中でつくられていたといいます。平安時代、少なくとも貴族社会にお茶は定着していたと考えられます。
2.実はわび茶を始めたのは豊臣秀吉だった!

黄金の茶室は接客用で、自分用は山里丸
天下人・豊臣秀吉は黄金の茶室をつくるなど、権力と財力にまかせてきらびやかなものを好んだという印象があります。一方、その対極にある「わび茶」の祖は千利休だというのが定説です。
しかし、中村先生は「ひなびたわび茶をはじめたのは秀吉かもしれない」と言います。これをうかがわせるものに「山里丸(やまざとまる)」があるそうです。山里丸とは、秀吉が大坂城や九州の名護屋(なごや)城に好んでつくらせた草庵風の建物のことで、茶会も行なわれました。また大坂城の発掘品には、黒や焦茶の茶入や茶碗もあり、わび茶の風情を思わせるそうです。
一方、黄金の茶道具は秀吉が関白となった返礼に、天正13年(1585)、宮中で正親町(おおぎまち)天皇に献茶をする際につくられています。当時、高価な唐物の茶道具が上等品とされていましたが、いくら高価とはいえ中古品。畏れ多くも天皇が口にする道具は新品でないといけません。茶道具はすべて新調され、建水、柄杓立てなどが黄金製だったという記録があります。
黄金の茶室は可動式で名護屋城へも運ばれましたが、用途は外国使節などの接客用。山里丸こそが秀吉の好みで、安らげる空間だったのではないかと中村先生は言います。千利休は秀吉の茶道指南で、もちろん茶の湯の名人でしたが、本来が商人だったのと、人に合せるのが天才的に巧みだったので、秀吉の好みをくみ取ってわび茶を追究した可能性がある、というのが中村先生の推論です。
3.時代の流れを読み取る天才クリエイターとは?

茶の湯の世界に新しい価値をプロデュース
千利休はわび茶の祖とされ、秀吉に取り立てられ、草庵の狭い茶室で地味な茶道具を用いる、極限の「侘び寂び」を追究したストイックな芸術家というのが定説です。
しかし利休は、そもそも堺の商人です。当時の堺は、中国からの高価な茶道具を含め、目新しい南蛮物はみな、堺を通って大坂や京都へ運ばれました。非常に活気を帯びたその町で、利休の生家は倉庫業を営んでいたといいます。
当然、目利きの商人でもあったはずで、それをうかがわせるものとしては、宇治のお茶屋との取引記録があり、協力して販路を広げていた可能性もあるとのこと。また茶人や戦国武将らの間では自ら茶杓を削ることが行なわれましたが、利休は、茶杓を下削りする工房を営んでいて、それは下削りをもとに茶杓を仕上げる需要に応えたものだったとか。黒茶碗をはじめ、茶道具を発注するなど、時代や権力者の好みを読み、茶の湯の世界に新しい価値をプロデュースできるクリエイター精神を持った人物が千利休でした。それも商いとして成立させる才覚を持っており、秀吉を支える政商であった可能性もあるそうです。
4.まとめ
いかがでしたか?平安時代の公家の日記にもお茶の記載があったり、豊臣秀吉がわび茶を始めていたり、千利休は時代の流れを読み取る天才クリエイターだったり。これまでのお茶の歴史の常識が覆るかもしれない説をご紹介しました。中村先生によると、一次史料から歴史として見直す研究はまだこれからとのことですが、今後新たな発見や新説も期待できるかもしれません。