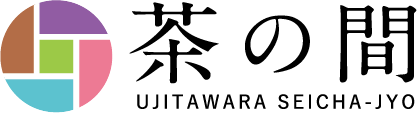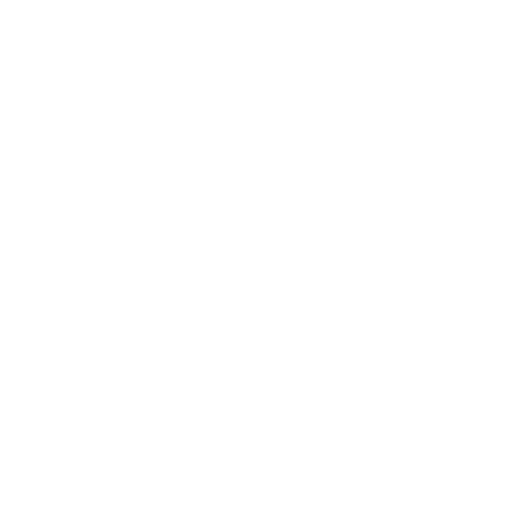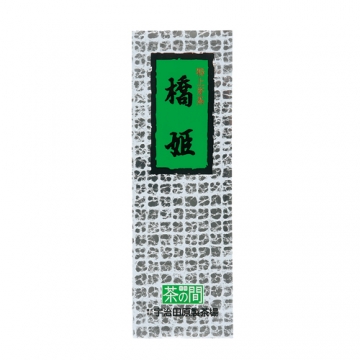夏目漱石おすすめ名作5選!お茶を愛した文豪の世界観を味わえる作品とは
2023.08.01
夏目漱石は明治から大正にかけて活躍した有名な小説家。『吾輩は猫である』『坊っちゃん』などの小説を書いています。そんな日本を代表する文豪、夏目漱石は実はお茶好きで知られており、小説にもなんどもお茶の描写が出てきます。
そこで、夏目漱石のおすすめ作品の中から、お茶への思いが表れている作品をさらに厳選して5つご紹介。

目次
1.夏目漱石の生い立ち
夏目漱石は1867年に、江戸の馬込(現在の東京都新宿)で、夏目直克と千枝の末子・金之助として生まれました。生まれてすぐに養子に出され、養子先の両親の離婚によって9歳のときに夏目家へ戻るなど、複雑な幼少期を過ごします。
10代から大学予備門(後の第一高等中学校)進学を目指して英語を学び、1884年に入学。そこで親友となる正岡子規と出会い、漢詩の創作や評論といった文学活動を行ないました。1890年に東京帝国大学(後の東京大学)英文科に進学。
大学卒業後、教職に就きましたが、やがて文筆業に専念することになります。代表作となる『吾輩は猫である』を、1905年に発表。1907年に朝日新聞に専属作家として入社します。その後も執筆を続け、多くの作品を発表しますが、1915年に大病を患い、49歳で亡くなります。
2.夏目漱石の作品の魅力
丁寧に綴られる心情描写を通して、人と人との関わり、生と死についてなど、普遍的なテーマを感じられるのが夏目漱石作品の魅力です。
また、それまでの日本文学で主流だった自然主義文学とは異なる作風で、エンターテインメント性が高いのも特徴です。現実をありのまま描くだけでなく、『吾輩は猫である』のように現実を客観的に観察するような作風は余裕派と呼ばれ、日本文学に新たな流れを生み出しました。
また禅宗の影響を受け、その思想が垣間見られる作品もあります。禅とは関わりが深いお茶を飲むシーンがよく出てくるのも夏目漱石作品の特徴です。
3.夏目漱石の名作5選!お茶への思いが表れている名シーンも
夏目漱石が生み出した数々の作品の中から、お茶が印象的に使われている5つのシーンをご紹介します。お茶好きで知られる漱石の綴るお茶の味わいに触れてみてください。
❶草枕(くさまくら)

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」からはじまる『草枕』は、世間の住みにくさを嫌い旅に出た青年画家を主人公に、非人情の境地を描いた夏目漱石の初期の作品です。
『草枕』はお茶のシーンが多いことで有名です。まずは下で紹介する文章を声に出して読んでみてください。

文字を見ているだけだと、小難しい漢字が並んでいると思うかもしれませんが、音で聞くと心地よく聞こえてきませんか? これは、美文(びぶん)という近代文学の文体系統の一つを意識して書かれたもの。美文は、耳で聞いた心地よさを重視する文体で、音やリズムが流れるように響き、うっとりするような聴き心地です。『草枕』の主人公たち3人がお茶を飲むというそれだけの場面が、なんとも優美です。
また、『草枕』の文章では、お茶「一しずく」を細部まで描いています。漱石は、“凝縮した一滴を味わったら、それは全体を味わったことになる”という考えを持っていました。人生を長くだらだら味わうより、凝縮した時間、一滴を味わうほうがよいという思想は、『草枕』に描写された、凝縮したお茶の「一しずく」に通じるものがあります。

解説
引用したのは、主人公の青年画家が、とあるお寺で和尚らとともにお茶をいただく場面。流麗な文章で、「一しずく」に凝縮されたお茶のおいしさが見事に表現されています。
「閑人適意の韻事」とは、風流な人が気ままにする遊びのことであり、濃く甘いお茶を味わうことは、風雅なものであり、お茶はゴクゴクと飲むものではなく、じっくりと味と香りを楽しむものだと述べています。
❷虞美人草(ぐびじんそう)

1907年に東京帝大講師をやめて朝日新聞社に入社し、職業作家になる道を選んでからの夏目漱石の最初の小説『虞美人草』。
主人公の小野が、自我の強い女性・藤尾と、古風でもの静かな恩師の娘・小夜子との間で揺れ動く物語です。
美文を味わえる『虞美人草』では、母娘がお茶を飲む場面でさえも、美しく魅せてくれます。冷めきった出がらしのお茶なんて、あまりおいしくないだろうに、それを表現する言葉の心地よい響きといったら! 文豪、夏目漱石のテクニックに脱帽するばかりです。

解説
華麗な語句で飾った美文が特長で、ヒロインの藤尾と彼女の母が茶の間でお茶を飲むシーンも、美しい文章が流れています。
急須の中には、以前飲んだときの茶が残り、母が入れ直そうかと言ったが藤尾は断り、そのまま冷たい茶を茶碗に入れて飲み干した、という場面です。さらさらと並ぶ美しい言葉に潜む、お茶の冷たさと、藤尾の母に対する冷たい態度が重なり合い、うまくいっていない親子関係を象徴しています。
❸琴のそら音

『琴のそら音』は1905年に雑誌『七人』に掲載された短編。迷信好きのお婆さんと住む主人公が幽霊を研究している友人の津田を訪ねます。婚約者がインフルエンザだというと、津田から最近インフルエンザから肺炎になって死んだ親戚の若い女性の魂が出征中の夫に会いにいったという話を聞きます。その帰り道で出合う葬式や犬の遠吠えの声にだんだん不吉な予感が……という話です。
漱石は若い頃から禅宗に興味を持ち、27歳のときには、鎌倉にある円覚寺で参禅したこともあります。禅といえばお茶。禅院の生活には喫茶の習慣が溶け込んでおり、「喫茶去(まあ、お茶でもおあがり)」という禅語もあるほどです。そして、漱石の小説の中では、お茶を飲むことが、しばしば日常の象徴として描かれています。
『琴のそら音』で、友人の家で怪談話を聞かされた主人公。だんだん怪しげな、非日常な雰囲気が深まっていくなか、友人の「まあ、お茶でも飲もう」という一言が日常を象徴する役目を担っています。

解説
不吉な話を聞き、平常心を取り戻そうとお茶を飲もうとする主人公。しかし、友人の淹れたお茶を彼は飲めません。安い茶碗になみなみとつがれた出がらしのお茶は、学生時代からの気のおけない友人との関係と日常性の象徴を表しています。お茶を飲めないことで、徐々に不安に飲み込まれ、日常の判断力が揺らいでいく、主人公の動揺がうかがえるシーンです。
❹坊っちゃん

『坊っちゃん』は親譲りの無鉄砲で江戸っ子気質な主人公が、四国の地方に赴任して、中学校の教師になるお話。何度もメディア化され、国語の教科書にも採用された作品だけに、知っている方も多いのではないでしょうか。
漱石の小説では、登場人物たちがよくお茶を飲んでいますが、そのお茶は味が薄いことが多く、ときには粗茶(そちゃ)であることも。漱石が日常を描くお茶は薄味なのです。ところが、『坊っちゃん』の地方で出てきたのは、苦い濃い茶。お茶の味わいから、東京との違和感を表現しています。

解説
東京育ちの主人公は、引っ越し当初、とにかく地方では気に入らないことばかり。古い慣習から、学校の派閥争い、はてはお茶にまでケチをつけます。
『坊っちゃん』では、四国に赴任した主人公が、関東の薄いお茶に比べて、ここのお茶は苦そうだと懸念を述べ、四国に感じる東京との異質感を表しています。
❺吾輩は猫である

『吾輩は猫である』は「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」からはじまる、夏目漱石の処女長編小説。中学校の英語教師の珍野(ちんの)苦沙弥の家で飼われている猫の視点から、一家や友人、門下の書生たちの人間模様が風刺的に描かれています。
禅に影響を受け、形式ぶったものを嫌った漱石。上っ面だけをなぞった形だけのものを嫌い、禅問答もどきの手紙を、「お茶でも召し上がれ」と茶化してしまいます。

解説
引用は、苦沙弥先生に届いた天道公平の手紙から。手紙には、初めてナマコを食べた人、初めてフグを食べた人に対する賞賛とともに、神への非難や革命の心理が書かれているのですが、それが実に支離滅裂。まるで禅問答のような文章が続きます。
そこに出てくる「よろしく御茶でも上がれ」の一言。まるで、訪ねてきた僧との問答にすべて「喫茶去」と返した禅僧の逸話を茶化しているかのようです。
4.おわりに
お茶を飲む、ただそれだけの場面なのに、夏目漱石にかかれば、詩情溢れるシーンになったり、その場にいた人たちの関係性を象徴する名脇役になったり、はては深い思想を表現していたり…。
読めば読むほど、文学とお茶の魅力にはまっていきそうです。紹介した作品は、夏目漱石の魅力もお茶の魅力も詰まったおすすめばかり。ぜひ読んでみてください。