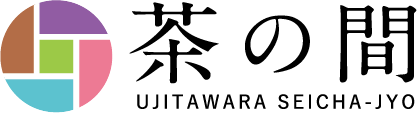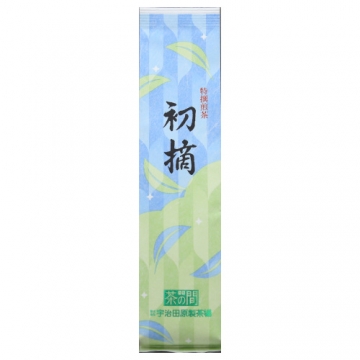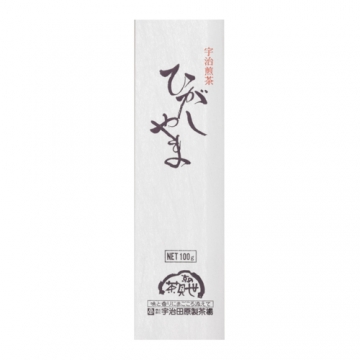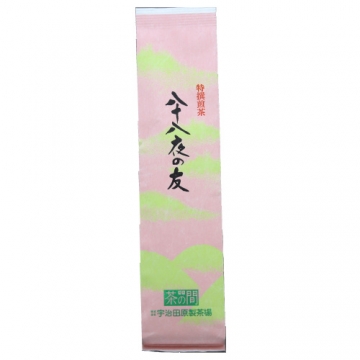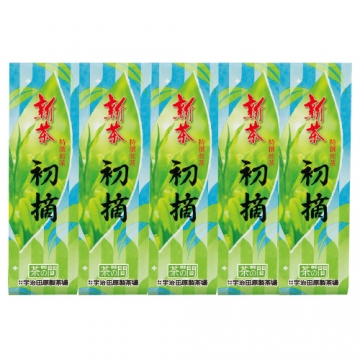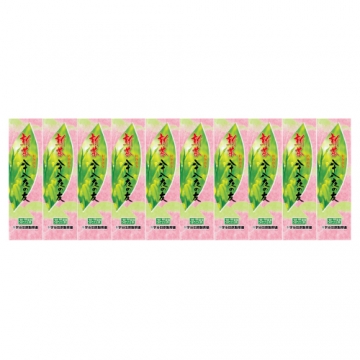新茶の楽しみ方を日本茶インストラクターが伝授!香りを味わう淹れ方とは
2024.06.01

いよいよ新茶の季節が到来! この時期だけの香り高いお茶の楽しみ方を宇治茶道場「匠の館」の日本茶インストラクター・村田範子さんに教えてもらいました。旬の香りを楽しむためのお湯の温度や浸出時間など、おいしい淹れ方で、新茶を味わい尽くしましょう!
目次
日本茶インストラクター 村田 範子さん

京都のお茶処・宇治から近い京都府木津川市出身の村田範子さん。子どもの頃、実家で飲んでいたお茶は番茶。20年ほど前、夫が退職し、二人三脚でやっていた建築事務所を閉鎖。新しいことを始めたいと日本茶インストラクターの認定試験を受験。見事合格し、現在は「匠の館」の館長補佐の1人として、約30名の日本茶インストラクターや日本茶アドバイザーを束ねつつ、訪れた人に宇治茶の魅力を伝えている。
1.日本茶インストラクターとは?

日本茶インストラクターは、日本茶に関するあらゆる知識や技術を持ち、一般の人々にお茶の淹れ方などを指導することができる、NPO法人日本茶インストラクター協会が認定する資格です。
主な活動内容は、日本茶教室の開催や学校・カルチャースクール等各種講習会講師、日本茶カフェのプロデュース、通信教育の添削講師、日本茶アドバイザーの育成・指導など。
認定試験では、全受験者の3割ほどしか合格しない、難関の資格となっています。日本茶インストラクターは、いわば、日本茶のプロフェッショナルです。
2.1年に1度の味わい、新茶ってどんなお茶?

❶若葉の清々しい香りとやさしい旨みがぎゅっとつまったお茶
茶農家さんが一年かけて大切に育てたお茶。冬を越して最初に収穫された新芽でつくられたお茶が「新茶」です。あたたかな初夏の日差しのもと、すくすくと育つお茶の新芽は、冬の間に蓄えた養分をたっぷり含んでいます。
「新茶には、厳しい冬を超えて旨みや甘みがぎゅっと凝縮されています。清々しい若葉の香りとやさしい甘みがあり、この時季にしか味わえない格別な魅力があります」と村田さん。
20年近くお茶に関わってきた今でも、新茶の季節は毎年心が弾むといいます。
「この時季になると、『今年の新茶はどんな味わいだろう!』とワクワクしますね。新茶を飲むと、目の前に若葉の茶畑が広がり、緑の風がさっと吹き抜ける様子が目に浮かぶんです。それが新茶の醍醐味で、幸せを感じる瞬間ですね」
❷新茶を楽しむなら、昔ながらの「普通煎茶」を選ぼう!

村田さんは、新茶期にこそオーソドックスな煎茶を楽しんでほしいと話します。
「煎茶は誰にも身近なお茶で、手軽に手に入ります。香りが高くすっきりとした風味が特長ですね」と村田さん。
煎茶の味わいには、製茶する際の蒸し時間が大きく関係しています。日本茶の葉は摘み取られたあと、蒸しの工程を経ます。この茶葉を蒸す時間の長さによって、茶葉の仕上がりが変わり、お茶を淹れたときの香りや味が決まるのです。煎茶の蒸し時間は約30秒。すっきりとした味わいが楽しめる、昔ながらのお茶です。これに対して、蒸し時間を約2倍にしたものは「深蒸し煎茶」と呼ばれ、より濃厚な味わいに。1960年頃に開発された深蒸し煎茶は現在、広く普及しています。
「深蒸し煎茶も濃厚でおいしいですが、私はやはり、新茶期には昔ながらの煎茶をおすすめしたいですね。爽やかな香りが一層際立ちます。少し湯冷まししたお湯で淹れれば、煎茶のおいしさがしっかり引き出されますよ。また、煎茶は淹れ方によって変化に富んだ味わいを楽しめるのも魅力です。基本の淹れ方を知った上で、いろいろ試してほしいですね」
3.江戸時代に誕生した「普通煎茶」はすっきりとした味わいが特長!

江戸時代に宇治田原町の永谷宗円が編み出した製法が煎茶の始まり。昔ながらの煎茶は深蒸し煎茶に比べて蒸し時間が短く、すっきりとした味わいが特長です。
旬を迎えた普通煎茶。そのおいしさを満喫するために、淹れ方のコツを教えていただきました。
❶温度で味わいが変わる!味と香りを楽しむ基本の淹れ方
新茶の香りを楽しむ淹れ方を村田さんに聞きました。
「煎茶は約60度のお湯で淹れるのが基本で、私はこれを“まったり系”の飲み方と呼んでいます。元気を出したいときは70~80度で淹れます。こちらはいわば“すっきり系”の飲み方です」
まったり系は甘みが強く出るため、ほっこりとリラックスするのによく、すっきり系は香りが立ち、シャキッとさせてくれます。新茶の香りを楽しみたいときはすっきり系がおすすめです。
「慣れてきたらその時々で、好みの淹れ方を選んでくださいね。ちなみに、水は水道水でよいですが、やかんでお湯を沸騰させたときは、すぐに火をとめてはダメですよ」と村田さん。沸騰したらやかんの蓋をとり、2~3分は沸騰を維持させるそうです。こうすることでカルキ臭が抜け、また水の中の空気が追い出されるのだとか。
「ちゃんと沸騰させたお湯を使うと、お茶の葉が底まで沈んで、水っぽくならず、しっかり浸出されるんです」
■ 基本の淹れ方(1人分の分量)
- 茶葉の量 5g
- お湯の量 60ml(温度60度)
- 浸出時間 1分
- 茶葉を急須に入れる。
- ゆっくり円を描くようにお湯を注ぎ約1分待つ。蓋はせず、ふわっと葉がゆるんで全体を覆うようになるのを目で確認する。
- 急須に蓋をして最後の一滴まで注ぎ切る。



❷1日かけてじっくり楽しむ、氷を使った応用の淹れ方

また、暑い時期は水出しや氷出しの冷たいお茶もおすすめです。
「低温で時間をかけて抽出し、甘みを引き出します。私流の氷出しの方法もありますので、応用編として試してみてくださいね」
そんな村田さん流の、氷を使った煎茶の楽しみ方をご紹介します。
■ 熱湯氷出し
急須いっぱいに氷を詰め、上に茶葉10gをのせ、上から熱湯を注ぐ。
■ 氷出し
急須に茶葉10gを入れ、上から氷をのせ自然に溶け出すのを待つ。溶けた分だけ少しずつ、1日かけて飲む、村田さん流の究極の飲み方。
4.外国人や若い人が注目! 世界に広がる宇治茶の未来

茶処として名高い宇治。豊かな水をたたえた宇治川が流れるここは、お茶栽培に最適な気候風土に恵まれた地なのです。
「宇治茶の特長は、旨みや甘みが強く出る覆下栽培を開発するなど、昔からさまざまな工夫がなされてきたことにあります。また、山間部は山あり谷ありの地形で、朝は霧が出たり、午後は陰になったりと、香りがよく個性あるお茶が育つ条件に恵まれているんです」と村田さんは話します。
小学生にお茶の淹れ方を教えることもあるという村田さん。子どもたちに聞くと、急須がない家庭も珍しくないのだとか。
「お茶というとペットボトルのお茶を連想する子も多いのが現状です。だからこそ、急須を使って淹れたお茶をもっと飲んでもらいたいですね。そのためには、お手入れが簡単な急須など、より手軽に急須のお茶が楽しめる方法の開発にも期待しています」
一方で、若者の間で急須のお茶や宇治茶への注目が高まりつつあるとも感じているそうです。
「日本の若い人が、急須でお茶を淹れることをスタイリッシュでかっこいい“新しい文化”として見直し、興味を持ってくれるようになってきたんですよ」と、村田さんは楽しげに話します。
広がりは国内にとどまりません。最近では「匠の館」を訪れる海外の方も増えているといいます。
「コロナ禍前は、来館する海外の方は、通りすがりやツアーの人がほとんどでしたが、今はSNSで広まったのか、宇治茶を体験したいと目的を持って来館されます。煎茶を淹れるとか、抹茶を点てるということが、憧れの日本文化になっているようですね」
宇治茶のおいしさやお茶を飲む豊かな時間の大切さをより多くの人に伝えるため、村田さんは日々、日本茶の魅力を発信しています。
■ 宇治茶道場「匠の館」
【電話】0774-23-0888
【HP】https://www.ujicha.or.jp
※宇治茶体験の申し込み、問合せは直接同店まで。
5.まとめ
お茶に魅せられた日本茶インストラクターの村田範子さん。1年に1度の新茶の季節は、長く日本茶に携わる村田さんにとっても心躍る季節です。特に新茶の香りを楽しむなら、昔ながらの普通煎茶がいいとおすすめしてくれました。
新茶の淹れ方も、お湯の温度を変えるだけで、「まったり系」と「すっきり系」の2つの楽しみ方があり、冷茶として楽しむ方法も簡単で挑戦してみたくなります。宇治茶の未来も語っていただき、お茶がもたらす豊かな時間の大切さを改めて感じました。